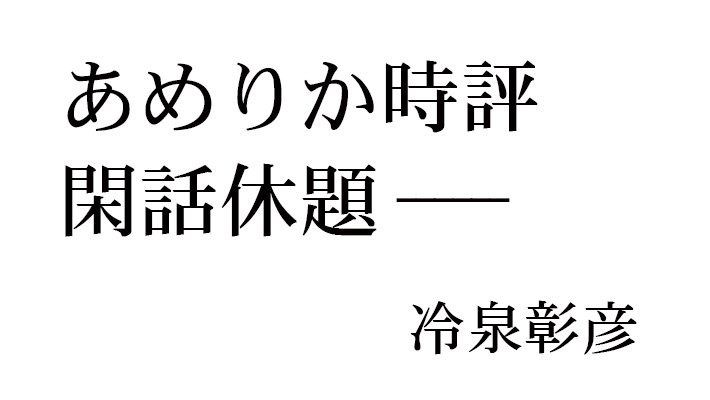岸田文雄政権が発足した。最大の売り物は、中間層の復権と所得倍増だという。岸田氏の率いる派閥「宏池会」の「創業者」である池田勇人が、1960年に掲げた「所得倍増論」を21世紀の現在に再現しようというのである。
けれども日本の置かれた環境は全く異なる。高度成長当時とは異なり、現在の日本経済は30年続く低迷の中にある。中国だけでなく、G7や韓国などと比較しても、明らかに日本は貧しくなっている、
そんな中で、岸田氏の「所得倍増」には期待がある。だが、その具体的な内容は明らかにされていない。岸田氏は「分配を強化して国内需要を喚起する」としているが、そもそも国全体で「稼ぐ」体制へ戻さなくては、所得倍増など不可能だ。分配強化による格差是正というのは、成長があってこその成果分配だからだ。
日本企業の中で、現在でも成功している企業は、多くの場合に海外を主要な市場にしている。自動車産業の場合、国内シェアは10数%であり、一桁という企業もある。電子機器、電子部品、工作機械なども同様だ。つまり成功している日本企業は多国籍化している。市場を国外に求めて成功しているのなら、昭和期と同様に現在の日本経済も高度成長していいはずだ。だが、そうはなっていない。
日本ブランドの自動車を例に取ると、北米市場向けの製品は、北米産がほとんどである。日本で協力会社が作る部品を中国製などと合わせて北米で完成車に組み上げている。従って、北米で車が売れると、北米での売り上げ利益が発生する。その利益はほとんど日本国内には還元されない。現地で再投資され、そして今は外国人の方が多い株主に配当されて終わりである。確かに日本企業が世界一になったりするのは誇らしいが、それで日本が豊かになるわけではない。
生産拠点を市場に近い国に移動する。現地生産というのは、1980年代から始まっていた。貿易摩擦を批判され、特に現地での雇用創出が政治課題になっていた中では、それが国策だったのである。では、その国策が間違っており、例えば中曽根康弘政権はアメリカの脅しに屈服することなく、自動車や電子機器の「集中豪雨的輸出」を維持すべきだったのだろうか。
そうではない。国の産業構造には発展の歴史が必然である。例えば、自動車産業を空洞化させた後には、より付加価値の高い宇宙航空産業へのシフトが進められるべきだった。また、80年代の英国がサッチャー改革で金融大国として復活したように、日本も高度な教育を受けた人材の厚みを生かして金融立国へと進むことは可能だったはずだ。何よりも、電子機器のイノベーションで世界を牽引していた日本は、90年代以降のIT革命でも中心的な位置を占めるべきだった。
だが、そうした「より知的な」「より付加価値の高い」産業への移行に、日本は失敗した。というよりも失敗し続けたし、反対に少しでも成功の芽が出れば、変化を恐れる勢力によって摘み取られ続けた。国力の喪失は、そのような30年間の失敗の積み重ねの結果である。具体的には、資産保有者の高齢化によるリスク投資の喪失、そして中進国型の教育を先進国対応へと変更できなかった国策の遅れが原因であった。
その結果として、日本はここまで追い込まれるまで、見事なまでに変われなかったのである。そこには、問題に気付いた側は衰退や滅亡への恐怖から、焦って「不連続な改革」を要求し続けたという「敗北の歴史」が重なる。改革要求が軋轢を生み出すことが分かっていながら、改革勢力は対決に勝利する戦略戦術に欠けていた。つまり、日本が貧困化した原因の一端は、主張は正しくても政治的に勝てない改革勢力の力不足にあったとも言える。
その意味で、改革型の河野太郎氏が、一見すると中道穏健派の岸田氏に敗北した今回の政局は、もしかしたら歴史の転換点になるかもしれない。再分配による中間層の復活などという「甘い言葉」で表面を塗りたくりながらも、岸田氏は教育や人材抜擢、あるいは金融政策における非連続的な変更を、静かに進める決意を持っているのかもしれない。そうでなくては「所得倍増」などできないことは、百戦錬磨の岸田氏には分かっていると信じたい。
(れいぜい・あきひこ/作家・プリンストン在住)