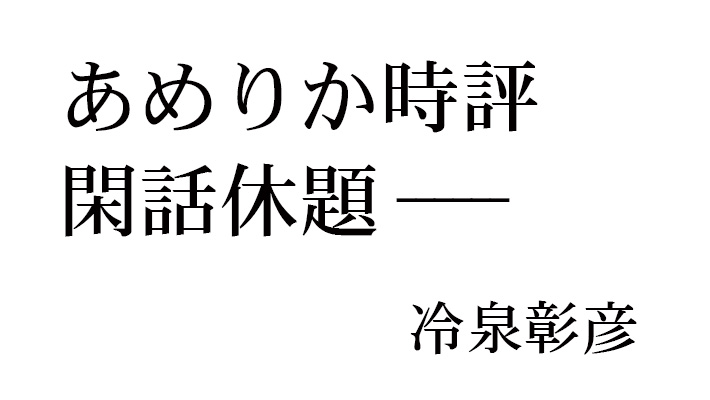あめりか時評閑話休題 冷泉彰彦
1995年1月の阪神淡路大震災では、被災地は復興した。勿論、失われた生命は還らないし、街の繁栄が100%回復したわけではない。何よりも心身に傷を負った人々の痛みは消えてはいない。けれども、倒れた高速道路も、潰された地下鉄駅も、破壊された新幹線のトンネルも、短期間のうちに修復された。震災を機に厳しい耐震基準が全国で適用されるようになり、防災・減災の体制は向上した。
だが、丁度10周年を迎えた2011年の東日本大震災に関しては状況が異なる。過疎高齢化と経済衰退という急降下中のジェットコースターの中で起きた震災という違いがまずある。この点を全く理解していなかった当時の民主党政権により、メリハリのない復興事業が進められた。巨大な防潮堤が建設され、住宅地は新たに高台に造成されたが、流出した人口は戻らなかった。巨費を投じた建造物は、災害の恐怖と、人口減少の恐ろしさを象徴するモニュメントとして後世に伝えられることとなった。
東日本大震災の残した問題は、具体的な復興の失敗だけではない。震災は日本という国の「国のかたち」そのものに深い傷を残した。被災地だけでなく、国の根幹の部分を傷つけ、その傷は今でも国を揺さぶり続けている。
1つは感情論への歯止めが外れたという問題だ。
被災地に千羽鶴を送るのは失礼だという議論がある。今では定着しているが、東日本大震災が契機だった。避難所へ古着を送るのも迷惑だし失礼、そんな議論も同じである。実務的には正しい指摘かもしれない。確かに大量に届く物資は迷惑になることがある。問題は3・11を契機として「負の感情」、つまり「千羽鶴を送られると惨めな気持ちになる」とか「古着の贈呈は上から目線だ」といったネガティブな感情論が解き放たれたことにある。
つまりお行儀よく「我慢」する必要はなく、堂々と「千羽鶴は惨めだから止めてくれ」という言葉を語って良いことになったのである。賛否両論はあるだろう。そのぐらいに、被災地の傷は深かったという理解がまずは必要だ。だが、一旦解き放たれた感情論は勢いを持つこととなった。津波で倒壊した市役所庁舎を震災の記憶として保存するか、あるいは見たくない悲劇の象徴として取り壊すかという議論もあったが、より深い傷を抱えた後者の意見が通る、そんな風潮も3・11の遺産と言える。
福島第一原子力発電所の事故の影響を心配して、科学的な根拠もなく西日本へ移住したり、そのために子を連れて離婚したりという現象も起きたが、これも感情論が解き放たれた結果だ。今では日本で定着した「安全・安心の確保」と言う言葉もそうだ。安全と安心は違うのであって両者を確保しなくてはならない、つまり感情論に正式な社会的な位置が与えられたという意味であり、3・11以降の現象だ。そのために、日本における政策上の意思決定はより複雑化し、困難なものとなっている。五輪やコロナを巡る政治の迷走の原点はここにある。
2つ目はエネルギー政策の行き詰まりだ。
原子力発電所の再稼働は、3・11を契機として政治的に困難となった。菅政権が脱炭素社会を掲げた今は、化石燃料の使用も止めなくてはならないが、火力発電を止め、ガソリン車を止めるとなれば、水素の輸入しか道はなくなる。太陽と風力には日本の電源を支える能力はない。製造業を諦めて知的産業にシフトすることも選択肢だが、教育や価値観の変革が間に合うとは思えない。
そこで、政府は豪州に大規模な水素分解工場を作ってもらって、そこから専用船で日本に液体水素を運ぶ計画だ。問題は水から水素を分解するにあたって排出される二酸化炭素である。計画では地層内に永久的に埋設処分することになっているが、文字通り永久となる二酸化炭素の埋設を他国に依存するというリスクは不確実性を残す。
3・11の残した傷は深く、このままでは国にとっての致命傷となりかねない。10周年を契機として、まずは冷静な診断が必要であろう。
(れいぜい・あきひこ/作家・プリンストン在住)